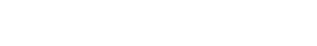鉄の鋳造のメリット・デメリットを分かりやすく解説

この記事では次の内容をまとめています。
・鉄鋳物の主な用途
・鉄の鋳造のメリット
・鉄の鋳造のデメリット
鉄鋳物の製造を依頼しようと考えている人が知っておくべきことを全てまとめました。
鉄鋳物の主な用途
この章では鉄鋳物が使われるよくあるケースをご紹介します。
自動車部品
耐摩耗性や耐久性に優れているため、エンジンブロック、カムシャフト、ブレーキローターなど重要な部品に使われ、自動車の安全性を支えています。
機械部品
摩耗や摩擦に強く、長期間の使用に耐えられるため、機械の歯車など、過酷な環境で活用される部品によく使われます。
建築資材
柱脚や金具など、建築物の構造を支える部材にも利用されます。
日本には木造の建物も多いですが、鉄骨造の方が耐久性は高いです。
調理器具
鉄製のフライパンや鍋、鉄瓶など、鉄が使われた様々な調理器具があります。
熱伝導性が高く、耐久性も高いことから、一般家庭だけでなく、レストランでも重宝されています。
マンホール
マンホールも鉄からできています。
重さがあるため簡単に動かせませんし、耐久性が高いので車両に踏まれても耐えることができます。
鉄の鋳造のメリット6つ
この記事では鉄の鋳造のメリットをご紹介します。
切削ではできない複雑な形状も可能
鋳造はあらかじめ型を作り、溶けた金属を流して固めることで成形する加工方法です。
そのため、切削加工や鍛造ではできないような細かく、複雑な造りでも実現できます。
中に空洞のある形でも問題ありません。
理想の形を1つの部品だけで作れるため、必要な部材の点数が減り、組み立てや接着の工程を省くことができます。
大量生産が可能でコストを抑えやすい
金型を用いた鋳造では型を繰り返し使えるため、大量生産が可能で、コストが安く済みます。
特に、自動車部品や機械部品のように規格品としてたくさん生産されるものは鋳造が向いています。
加工時間を大幅に短縮できるため、生産効率は高く、労働コストやエネルギーコストの削減にも繋がります。
ちなみに、砂型の場合は1回1回崩されるので大量生産には向きませんが、試作品製作や少量生産には合っています。
製品の品質が安定する
同じ型を使い回すことにより、形状やサイズのバラつきが少なくなり、製品の品質が安定します。
大量生産しても精度が一定に保たれるため、規格が厳しい分野では大きなメリットとなるでしょう。
強度が高い
鉄鋳物は長期にわたって高い強度を維持できます。
そのため、重量のかかる機械部品や建築資材でよく使われています。
厚さや形状を調整することで、必要な部分にさらに強度を持たせることも可能です。
丈夫で劣化しにくい鉄鋳物を採用すると、メンテナンスや交換の手間を省けるメリットもあります。
材料の無駄が少ない
鋳造では完成した鋳物は多少加工されるものの、ほぼそのまま製品となります。
一方で、切削加工の場合は元の素材から不要な部分をどんどん削り落としていくやり方なので、材料の無駄が発生します。
そのため、鋳造では材料費を抑えることができます。
リサイクルできる
・使用しなかった溶湯(金属を溶かしたもの)
・加工の際に切り落とした廃材
・不良品
・使用済みの鉄製品
を再び溶解することで再利用できます。
このように環境に優しく、持続可能性が高いのも強みです。
鉄の鋳造のデメリット3つ
この章では鉄の鋳造のデメリットをご紹介します。
不良が生じやすい
鋳造は実は不良が生じやすい加工方法です。
溶けた金属を型に流し込む工程でガスの巻き込みや冷却のムラが発生すると、ひけ巣やヒビ割れといった欠陥が生じます。
また、溶湯の温度管理や注湯の速度を誤ると、寸法のズレが起き、指定の寸法通りに仕上がらないことも。
不良率が高まると歩留まりが悪化し、必要なコストが増えてしまいます。
製品の質が職人の腕に左右される
鋳造は不良が発生しやすいものの、全ての業者に当てはまるわけではありません。
こうした不良を防ぐには経験と勘が重要です。
つまり、発生率は職人の腕に左右されるということです。
そのため、長年鋳造に携わっている職人がいる業者を選ぶことが大切です。
また、業者と長期的に取引したい場合は、技術継承ができているところを選ぶことも大切です。
型の製作に時間がかかる
鋳造では、まず鋳型を作る必要があります。
型の製作には設計から仕上げまで多くの工程があり、時間とコストがかかります。
特に複雑な形状や高精度を求められる場合、製作期間は長期化しやすいです。
一方で、鍛造や切削の場合はこうしたプロセスがありません。
鉄の鋳造の流れ5ステップ
この章では鉄の鋳造の工程をご紹介します。
型の作成
まず金属を流し込む型を作ります。
様々な種類がありますが、主に使われるのが砂型と金型です。
造型作業は完全に手作業で行われることもあれば、完全に自動で行うこともあります。
溶解
金属を溶かして液体状にします。
鉄の融点はおおよそ1500度ですが、他の金属など、一緒に混ぜるものによって融点は変わります。
ここで適切な温度にすることで不良の発生率を低減することができます。
鋳込み
型に溶かした金属を流し込みます。
このとき、場所によって温度のムラが生じないよう、注ぎ込むスピードを調整することが大切です。
溶解と鋳込みは特に職人の腕に左右される工程です。
冷却
金属を冷やし固めます。
しっかり固まったら型を取り外します。
砂型の場合、振動を与えて崩します。
冷めるまでの時間は材料や鋳物の形状によって異なります。
仕上げ
・鋳物の表面についた砂をショットブラストで落とす
・バリ取りをする
このような仕上げ作業を行います。
製品によってはこの後
・アルマイト処理
・塗装
・メッキ
など、さらに表面処理を行うこともあります。
鋳鉄と鍛鉄の違い
この章では項目別で鋳鉄と鍛鉄の違いをご紹介します。
なお、ここでの鋳鉄は「鉄の鋳物」を意味します。
製造法
鋳鉄は鋳造によって製造されたもの。
一方で鍛鉄は鍛造によって製造されたものです。
鍛造とは金属を叩くことで加工するもの。
叩かれることで金属は内部の隙間がなくなり、結晶の構造が整います。
特性
鍛鉄は鋳鉄に比べて強度や粘り強さにおいて優れています。
そのため、より強度が必要とされる場合は鍛鉄の方が望ましいかもしれません。
修正のしやすさ
鋳物の大幅な修正は難しいです。
なぜなら、鋳造が終わった時点でほぼ完成に近い形になっているからです。
一方で鍛造は何度も叩くことで形を変えていく製造法なので、鍛鉄の方が修正や調整がしやすいです。
純鉄・鋼・鋳鉄の違い
この章では鉄の鋳造で使われる主な材料をご紹介します。
なお、ここでの「鋳鉄」は先ほどとは異なり、鉄を使った鋳物に使われている材料を指します。
純鉄
炭素の量が0.02%未満の鉄です。
純鉄はあまり強度は高くなく、酸化もしやすいことから、鋳造ではあまり使われません。
これからご紹介するように炭素が足された鉄が使用されます。
鋼
炭素の量が0.02~2.14%の鉄です。
炭素の割合が多い分、純鉄に比べると強度、耐摩耗性が高いです。
また、粘り強さに優れています。
鋳鉄
炭素が2.14~6.67%の割合で含まれた鉄です。
鋼よりもさらに強度や耐摩耗性が優れるものの、粘り強さは低く、折れたり割れたりしやすいです。
まとめ
鉄の鋳物は強度や耐久性が高いことから、自動車部品や機械部品など私達の周りで広く使われています。
鋳造は複雑な形状も可能ですし、金型を使い回すことで大量生産もできるため、コストパフォーマンスの良さを求めるなら鋳造はおすすめです。
気になる方は一度お近くの鋳造業者に問い合わせてみましょう。
ブログ一覧へ