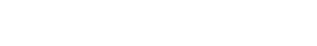真鍮鋳造とは?基本の特徴・工程・用途を解説

この記事では次の内容をまとめています。
・真鍮とは?
・真鍮鋳造の工程6ステップ
・真鍮鋳物の用途
真鍮を用いた鋳造をしたいと考えている方が知っておくべきことを全てまとめました。
真鍮とは?
真鍮は銅に亜鉛を混ぜた合金で、「黄銅」や「ブラス」と呼ばれることもあります。
真鍮の中にも様々な種類があり、銅と亜鉛の含有量によって合金の特徴は変わります。
例えば、銅の割合が大きければ大きいほど、銅らしい赤みのある色になります。
さらに、他の金属を足すことで、耐食性、強度、加工性などを高めることも可能です。
美しい光沢と加工のしやすさから、装飾品、楽器、機械部品など幅広い用途に用いられています。
真鍮の主な種類
この章では真鍮の主な種類をいくつかご紹介します。
C2600(黄銅1種)
亜鉛の含有量は30%ほど。
展延性、絞り加工性、耐食性、メッキ加工性に優れています。
金属板、端子コネクター、装飾品などに用いられます。
C2680(黄銅2A種)
基本的な性質はC2600と同じですが、C2680の方が亜鉛が少し多く含まれています。
ハトメ、スナップボタン、魔法瓶、カメラ、配線器具、端子コネクターなどによく用いられます。
C2700(黄銅2種)
亜鉛の含有量は約35%。
C2600に比べて強度が高いです。
色が綺麗なことから、建築材料や装飾用品として使われることが多いです。
C2801(黄銅3種)
亜鉛の含有量は約40%。
強度や展延性が高いのが特徴です。
用途としては配線器具、ネームプレート、計器板などがあります。
C3604(快削黄銅2種)
快削黄銅とは被削性を高めるために鉛を添加した真鍮です。
切削加工を得意としており、機械部品、歯車、バルブなどによく使われます。
ただし、近年は鉛の安全性の問題から、鉛レスで且つ快削黄銅のような性質を持つ金属のニーズが高まっています。
真鍮鋳造の工程6ステップ
この章では砂型鋳造によって真鍮の鋳物を作る工程をご紹介します。
原材料の調達
鋳造に用いる原材料を用意します。
真鍮は主に銅と亜鉛から成る合金ですが、用途に応じて鉛やスズなどの他の金属を加えることもあります。
業者によって取り扱っている金属の種類は異なります。
砂型の作成
まずは造型用の砂を作ります。
砂にベントナイトや水を混ぜて、砂型に適した状態にします。
次に造型作業を行います。
木型などの型に砂を詰めた後、型を慎重に取り外すことで、鋳造用の砂型を完成させます。
溶解
鋳造で用いる金属を溶かします。
欠陥のない鋳物を作るにはここで適切な成分配合を行うことが欠かせません。
途中で浮き上がってきた不純物は取り除き、純度を上げます。
注湯
1つ前の工程で溶かした金属を鋳型に注ぎ込みます。
途中で金属が冷えると不良の原因となるため、注ぎ込む際のスピードがとても重要です。
職人の経験や勘に頼る部分が大きい工程です。
バラシ
注湯が終わり、金属が冷めたら、砂型に振動を与えて崩します。
鋳物の表面に残っている砂はショットブラストと呼ばれる機械で取り除きます。
仕上げ
不要な部分を切削したり、磨いたりして、製品の仕上げを行います。
真鍮鋳物の用途
この章では真鍮鋳物が使われる例をご紹介します。
建築金物
綺麗な見た目が特徴の真鍮。
それを生かしてドアノブや手すりといった建築金物に使われ、高級感を演出します。
お寺の装飾品や仏具にも使われます。
真鍮は耐久性に優れているため、このように人の手が触れることが多いものには向いています。
硬貨
真鍮が使われている一番身近な例といえば5円玉。
硬く、耐食性が高い真鍮はいろいろな人の手に渡りながら長年使われる硬貨に適した素材と言えます。
新しい5円玉はピカピカで綺麗な一方、古いものは錆びたような色をしていることがあります。
このように時間が経つと色味が変わるのは真鍮の特徴の1つです。
楽器
トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバといった金管楽器には真鍮が使われています。
真鍮特有の音の響き方と加工性が金管楽器に向いているからです。
光沢のある見た目はブラスバンドの華やかさを演出します。
ちなみにブラスバンドの「ブラス」は真鍮を意味します。
電子部品
・電気伝導性が高い
・腐食に強い
・加工性に優れている
・耐久性に優れている
こうした特徴を生かして電子部品に使われます。
例えば、C2600、C2680は端子コネクターによく使用されています。
機械部品
耐摩耗性、強度、加工性に優れる真鍮は、歯車やバルブといった機械部品に幅広く使用されます。
水回りの部品
耐食性が高い真鍮は水回りの部品にも多く使われます。
例えば、バルブ、弁、蛇口などです。
給水器具に真鍮を使うことで意匠性を高める効果もあります。
ちなみに、最近は水回りの器具は人体への影響を考えて鉛レス素材が用いられる傾向があります。
アクセサリー
ピアス、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリーにも人気の素材です。
ボタンなど服飾の一部に使われることもあり、ファッションのアクセントとして機能します。
金に似ている見た目ながら安価な素材なので重宝されています。
真鍮のメンテナンス方法
真鍮は最初は光沢のある綺麗な見た目をしています。
しかし、時間の経過と共に、酸化によって落ち着いた色になったり、緑色の錆が現れたりと、見た目が変化します。
敢えてこの変化を楽しむ人もいますが、ずっと新品のような状態に保ちたい場合はメンテナンスが大切です。
その方法としては以下のようなものがあります。
・定期的に布で汚れを拭き取る
・研磨剤で磨く
・使用前に表面を保護する処理を行う
真鍮とメッキの違い
メッキは異なる素材の表面に金属を薄くコーティングする加工のこと。
例えば、比較的安価な金属に金や銀でメッキ加工をすると、本物の金や銀でできた金属のように見せることができます。
真鍮とメッキの見た目は似ていて、区別がつかないこともあります。
メッキは長く使用するうちに剥げて、元の金属の色が見えるようになります。
一方で、真鍮は素材そのもので、中まで同じ金属なので、多少の経年劣化はするものの、手入れをしっかりすれば元の輝きを維持することができます。
真鍮鋳造を発注するときのポイント3つ
この章では真鍮を使った鋳造を発注するときに押さえるべきポイントをご紹介します。
用途に合った材料を選ぶ
先ほどもご紹介しましたが、一言で真鍮と言っても、様々な種類があり、添加されている成分や、成分の配分割合が異なるため、それぞれ特性も異なります。
そこで、真鍮鋳造を依頼するなら、用途に合う素材を選ぶことが大切です。
真鍮についてあまり詳しくない・・・という場合は業者に相談して最適なものを選んでもらいましょう。
仕上がりの要望を細かく伝える
どんな仕上がりにしたいのか、イメージを細かく伝えることで、理想通りの鋳物が完成します。
例えば
・形状
・求める精度の高さ
・強度
・表面の状態
などを伝えましょう。
コスト
費用は真鍮鋳造をする上で特に気になるポイントではないでしょうか。
鋳造では製品を作る際に必要な素材の値段だけでなく、
・型の製作費
・試作品の製作費
・仕上げの加工費
も必要です。
また、ロット数によって値段が変わることも。
まずは業者に見積もりをとってもらいましょう。
まとめ
真鍮とは銅と亜鉛の合金のことで、黄銅と呼ばれることもあります。
光沢のある独特な綺麗な見た目を持ち、且つ、加工性や耐食性の高さなど、様々な性質があるため、アクセサリーから機械部品まで幅広い用途で用いられます。
真鍮による鋳造を考えているなら、まずは専門の業者に相談し、用途や仕上がりのイメージを共有しましょう。
ブログ一覧へ